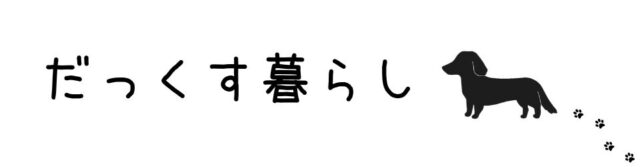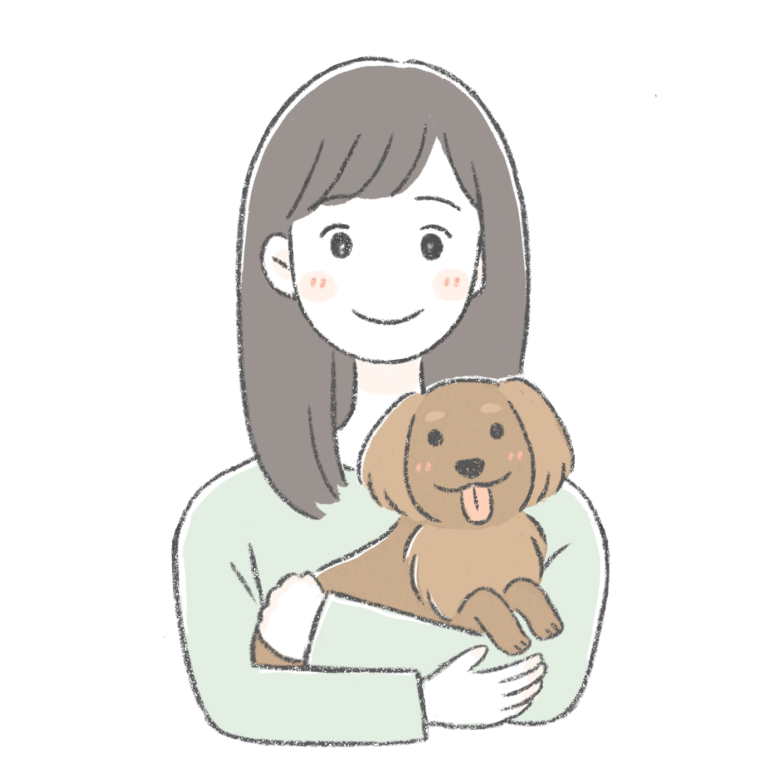愛犬の口臭が臭いと感じることはありませんか?
愛犬の口臭が魚臭い理由は3つあります。
- 歯周トラブル
- 内臓疾患
- 食べ物のにおい
においによって原因は変わりますが、中でも多くが歯周トラブルです。
歯周トラブルは歯のケアをすれば防ぐことができ、口のにおいも改善できます。
この記事では対策もまとめているので口臭が気になるならぜひ読んでくださいね。
愛犬の口臭が魚臭い原因

口臭が魚臭い原因は3つあります。
- 歯周トラブル
- 内臓疾患
- 食べ物のにおい
原因によっては命に関わることもあるので、愛犬の口臭は何が原因なのかを考えてみてください。
病気の可能性があったら獣医師に相談しましょう。
歯周トラブル
愛犬の口臭が魚臭い一番の原因は歯周トラブルです。
歯周トラブルには歯垢、歯石、歯周病、根尖膿瘍(歯根に膿がたまる病気)があります。
この中で口が臭くなる原因は細菌です。
歯垢1gの中には細菌が数億個入っています。
細菌が口の中のタンパク質を分解するときに臭いが発生します。
そのため歯垢や歯石が多ければ多いほど細菌も多くなるため口臭も強くなってしまいます。
根尖膿瘍になると膿がたまり膿の中はさらに多くの細菌が入っているため口のにおいはさらに臭くなります。
内臓疾患
胃・腸などの消化器や腎臓、肝臓の病気の可能性があります。
においによってどのあたりが悪そうかあたりをつけられるので参考にしてくださいね。
すっぱいにおい
すっぱいにおいがする場合、胃腸の不調が考えられます。
胃炎で胃液の分泌量が増えていると嘔吐したり胃液が逆流することもあります。
胃炎のほかにも胆汁の逆流、胃腸の炎症、胆道の炎症などがすっぱい口臭の原因になります。
アンモニア臭
口からアンモニアのようなにおいがする場合、腎臓・肝臓の異常が考えられます。
アンモニアは肝臓で分解されるため肝臓の機能が落ちると分解されずに体内にたまってきます。
腎臓では尿素とアンモニアを体の外に排出する働きがありますが、腎機能が低下するとうまく排出できなくなり体内にたまってしまいます。
このように肝臓や腎臓が悪くなると体内にアンモニアがたまり口臭として出てきます。
便のにおい
ひどい便秘がある場合は口の中から便のにおいがします。
ひどい便秘の場合、ただ出にくいだけではなく腸閉塞や腫瘍によって出口をふさがれている可能性もあります。
ただ、食糞癖のある子では口の中から便のにおいがする子が多いです。
食べ物のにおい
においの強い食べ物をあげるとにおいが口の中に残ることがあります。
今は魚が体にいいとされてサーモンやニシンなどが入っているフードがたくさんあります。
魚が入っているフードを食べると口の中が魚臭くなります。
口の中にフードのカスが残っていることが原因のひとつです。
他にもDHAやEPAのサプリメントは魚油を使っているため、食べることで口の中が魚臭くなります。
実際にわたしの愛犬もモエギキャップをあげ始めてから口が生臭くなりました。
噛んで飲み込んでいないのでおそらく胃の中で分解された魚油のにおいが口の中に出てきているのだと思います。
愛犬の口臭を軽減する対策

愛犬の口臭を軽減するためには先ほどあげた原因を取り除く必要があります。
まずは愛犬の口臭がどこから来ているのかをはっきりとさせましょう。
病気が考えられるときは動物病院の先生に相談してくださいね。
歯周病が原因の場合は口の中のケアをすることで口臭を減らすことができます。
歯磨きができることが一番良いですが、歯磨きは苦手な子が多いので愛犬ができる範囲のことをやってみましょう。
スケーリングをする
口臭の原因が歯周トラブルの場合、歯石がついていることがほとんどです。
歯石がついているならまずは歯石を取って歯をきれいにします。
歯石が付いた状態で歯磨きをしても歯石は歯ブラシで取れないし、歯石の中に細菌が入っているため口臭はなくなりません。
逆に歯ブラシで歯肉の隙間から細菌を奥に押し込んでしまう可能性もあります。
そこでまずは動物病院でスケーリングをします。
基本的にスケーリングは全身麻酔です。
今は無麻酔スケーリングも流行っていますが、無麻酔でやるとわんちゃんが動いた時に歯茎や唾液腺を傷つけてしまう可能性があります。
無麻酔だと歯周病菌が入っている歯周ポケットまできれいにできないのもデメリットです。
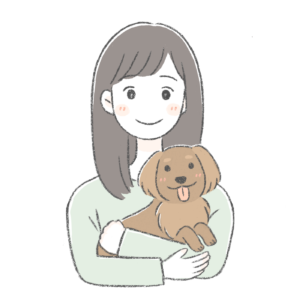
高齢だったり病気があり全身麻酔が難しい子は無理に無麻酔スケーリングせずにできる範囲の歯磨きケアをしましょう。
スケーリングすれば歯石や歯垢がなくなり口臭もなくなります。
歯石がなくなったら今度は歯垢、歯石が付かないように歯のケアをしましょう。
サプリメントをあげる
歯磨きができる子は歯磨きするのが一番ですが、全く口を触らせてくれなかったり、噛もうとする子はサプリメントでケアしましょう。
歯磨きサプリメントには口臭を抑える成分や口の中の菌のバランスを整える働きのある成分が入っています。
例えば、このこのふりかけはにおいを吸着するなた豆や口の中の細菌のバランスを整える乳酸菌、唾液の分泌を促すポリグルタミン酸などが入っています。
どれも犬用歯磨き粉にも使われている成分です。
この粉末をごはんにかけるだけで歯のケアができますよ。
こちらのサプリメントも人気です。
しかし、歯磨きサプリメントには注意点もあります。
粉末状のサプリメントをあげるだけでは物理的に歯垢を落とすことはできません。
お口の環境を整えて口臭を減らすことはできますが、正直、歯を磨けないと歯周病の予防は厳しいです。
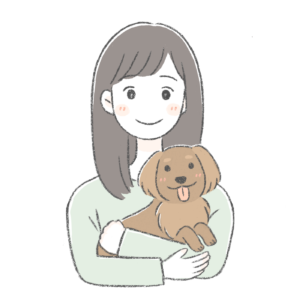
歯磨きサプリメントでケアしつつ、歯磨きができるように練習していきましょう。
歯磨きをする
わんちゃんの歯を守るためには歯磨きが必須です。
歯磨きが苦手な子は少しずつ慣らしていくと良いですよ。
歯磨きの練習には歯磨き粉を使うとスムーズにできます。
ドクターワンデルは歯磨き粉と歯磨きガムがセットになっています。
歯磨き粉をつけたガムを噛むことで歯ブラシで磨かずに歯をケアすることがコンセプトになっています。
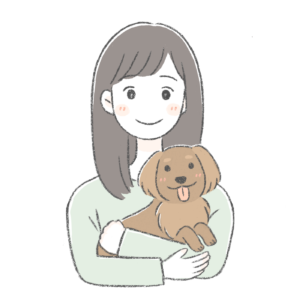
わたしのおすすめの使い方は本来の使い方とは少し違うので紹介しますね。
多くのわんちゃんは歯磨きガムが大好きです。
そこで、歯磨き粉をつけた歯ブラシで歯を磨いた後にご褒美として歯磨きガムをあげます。
そうすることで「苦手な歯磨き」が「おいしいものがもらえること」に変わっていきます。
最初は焦らず口を触るところから始め、歯を触ったり歯ブラシを少しだけ当ててみる、という感じで段階的に歯磨きに慣れさせていくとわんちゃんも嫌がらずにできるようになります。
何度も繰り返して歯磨きが嫌なことじゃないと理解できると歯磨きできる時間も長くなっていきますよ。
\ 公式サイトなら最大75%OFF /
歯ブラシが苦手でも続けられるデンタルケア
▼わたしがドクターワンデルを使った口コミはこちら
愛犬の口臭が魚臭い原因と対策まとめ

愛犬のお口が魚臭い原因は3つあります。
- 歯周トラブル
- 内臓疾患
- 食べ物のにおい
この原因に対する対策も3つです。
- スケーリングをする
- サプリメントをあげる
- 歯磨きをする
口臭をなくすにはまず、どんな原因で口が臭くなっているのかを見つけることが大切です。
原因が分かったら原因をなくす対策をしましょう。
大きな病気が隠れているかもしれないので「口が臭いのはしょうがない」ではなく、原因を見つけてケアしましょう。
ドクターワンデルなら歯磨きができないうちから手軽に歯のケアができ、歯磨きの練習もできますよ。